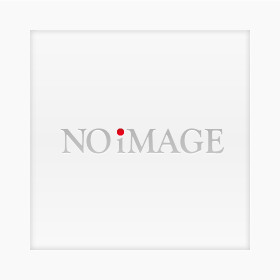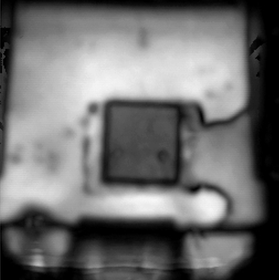金属部品の破損事故の原因調査が可能です。
金属材料が破壊する際、材料の性質、負荷応力、環境条件等の様々な要因に よって、破壊形態が変化します。破面を電子顕微鏡を使って詳細に観察すると、その破壊形態から破壊の原因をある程度特定することができます。破壊様式は、延性破壊、脆性破壊、疲労破壊、環境破壊の4つに大別されます。延性破壊は、破壊に到るまでに伸び等の大きな変形を伴う破壊です。脆性破壊は、 塑性変形せず速い速度でき裂が伝播する破壊です。疲労破壊は、繰り返し応力により徐々にき裂が進展する破壊です。環境破壊は、腐食性環境によりき裂の進展が著しく促進される破壊です。
この製品へのお問い合わせ
基本情報
破損事故対策のためには、事故原因を推定することが重要です。ここでは、破損品を調査するための基本事項を取り上げます。まず、破損状況の把握をします。破面上の錆、付着物は、破損発生時期を推定する上で重要な情報になります。次に目視などによる破面観察により、亀裂発生から破断に至るまでの大まかな状況を把握します。過大な荷重が加わり破断したのか、疲労なのか、 脆性破壊なのか、おおよそを把握することができます。その次に、目視などによる破面観察で推定した破損原因を明確にするために破面の微細部を観察し、亀裂発生状況、破壊の種類、亀裂伝播の方向を確認します。亀裂発生箇所における異物、欠陥の有無の確認も行います。さらに、必要に応じて金属組織の観察、硬さ測定を行うことにより、素材の状態に異常がないかを確認します。ここで金属の破壊機構は、延性破壊、ヘキ開破壊、粒界破壊、疲労破壊に分類されますが、この中で疲労による破壊が、破損事故の大部分を占めます。疲労亀裂は、微視亀裂が発生・初期伝播する第一段階から、亀裂進展が巨視的な力学的因子に支配される第二段階に遷移することで成長し、最終的に破断にいたります。
価格帯
納期
用途/実績例
金属部品の破損事故の原因調査
カタログ(2)
カタログをまとめてダウンロード企業情報
大同分析リサーチは、あらゆる材料分野で蓄積してきた信頼性の高い分析・解析技術と、広範囲な業界のお客様からいただいた課題をもとに、先進シンクタンクの構築を進めてまいりました。お客様の種々な課題に対し、最少費用と最短納期で問題解決を図ります。今後も最新鋭の設備と高度なマンパワーを駆使してお客様の研究開発を支援し、未来を豊かに彩る製品づくりのお手伝いをさせていただきたいと考えています。