1~45 item / All 71 items
Displayed results
Added to bookmarks
Bookmarks listBookmark has been removed
Bookmarks listYou can't add any more bookmarks
By registering as a member, you can increase the number of bookmarks you can save and organize them with labels.
Free membership registration
Contact this company
Inquiry Form1~45 item / All 71 items
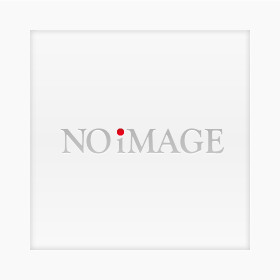
This time, at the request of the Japan Isotope Association's newsletter "Isotope News," I contributed an article on "Analysis of the Fine Structure of Living Cells Using Small-Angle Scattering." Contribution: Fine Structure Sensing of Living Cells Using Small-Angle X-ray Scattering Author: Katsu Nakata, Toray Research Center, Inc. Kazuaki Matsumura, Japan Advanced Institute of Science and Technology Journal: Isotope News "TRACER," April 2025, No. 798, pp. 22–25 https://www.jrias.or.jp/books/cat3/list.html In this issue, we introduce examples of evaluations using small-angle X-ray scattering as a method to measure the nanoscale fine structure of cells while they are alive, under various extracellular environments.
Added to bookmarks
Bookmarks listBookmark has been removed
Bookmarks listYou can't add any more bookmarks
By registering as a member, you can increase the number of bookmarks you can save and organize them with labels.
Free membership registration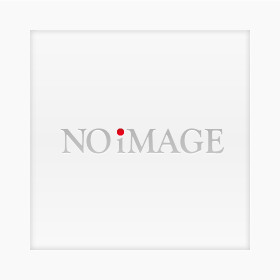
Our company (hereinafter referred to as "TRC") has established the "Integrated Bioanalysis Research Department" as of April 1st, by consolidating departments responsible for structural analysis, characterization analysis, stability testing, and quality testing, in order to strengthen support for the research and development of diverse biopharmaceuticals represented by antibody drugs, nucleic acid/mRNA drugs, and cell therapies. Traditionally, TRC has provided analytical support at various stages of drug development, including structural analysis and method development to support drug discovery research, pharmacokinetic analysis under GLP conditions, and stability testing under GMP conditions. However, in response to the recent acceleration and diversification of drug development, we determined that an integrated organization of the traditional analytical departments would be effective, leading to the establishment of the new organization. The Integrated Bioanalysis Research Department brings together staff engaged in analysis at all stages of drug development to provide high-quality analytical services to our customers in a seamless manner. This will enhance the sophistication of the ever-evolving analytical technologies for biopharmaceuticals while strengthening our proposal capabilities to customers and aiming for further evolution of our services. Under the fundamental principle of "contributing to society with advanced technology," TRC will continue to grow together with our customers through the analytical expertise and quality cultivated over many years, contributing to the life sciences field, including drug development.
Added to bookmarks
Bookmarks listBookmark has been removed
Bookmarks listYou can't add any more bookmarks
By registering as a member, you can increase the number of bookmarks you can save and organize them with labels.
Free membership registration
Our company (hereinafter referred to as "TRC") has launched a service for pharmaceutical applications of extracellular vesicles as part of our analytical support for the social implementation of extracellular vesicles. Extracellular vesicles are small vesicles (small bag-like structures enclosed by a membrane) secreted by cells that transport biomolecules such as proteins and nucleic acids, playing a crucial role in intercellular communication. In recent years, the development of drugs utilizing extracellular vesicles as drug delivery systems (extracellular vesicle drugs) has been advancing, but there are few companies capable of conducting analyses that meet the stringent standards for pharmaceutical applications, making the establishment of an analytical framework for drug applications urgent. Therefore, TRC has started a quality evaluation service for the development and application of extracellular vesicle drugs, contributing to the social implementation of extracellular vesicles.
Added to bookmarks
Bookmarks listBookmark has been removed
Bookmarks listYou can't add any more bookmarks
By registering as a member, you can increase the number of bookmarks you can save and organize them with labels.
Free membership registration
Our company (hereinafter referred to as "TRC") has introduced a system at our Shiga facility to re-liquefy helium gas used as a refrigerant in analytical instruments, in preparation for the helium crisis that has garnered particular attention in recent years. This has established a framework for the stable and continuous provision of specialized analytical services for nuclear magnetic resonance (NMR) and other ultra-low temperature measurements, which are essential for liquid helium. Helium is used in a wide range of fields, including superconducting magnets, medical devices, and scientific research, but it has become increasingly difficult to obtain in recent years due to a decrease in supply and a global increase in demand. At TRC, we have built a system to recover and reuse helium gas that vaporizes from NMR superconducting magnets and liquid helium containers, and we have begun operations. This allows us to provide stable services for NMR and ultra-low temperature measurements while contributing to the effective use of helium. TRC will continue to strive to provide sustainable advanced analytical services while responding to changes in the resource supply environment, based on our fundamental philosophy of "contributing to society through advanced technology." For more details, please check the related links.
Added to bookmarks
Bookmarks listBookmark has been removed
Bookmarks listYou can't add any more bookmarks
By registering as a member, you can increase the number of bookmarks you can save and organize them with labels.
Free membership registration
Our company (hereinafter referred to as "TRC") is the first domestic contract analysis company to launch a high-sensitivity analysis service for catalyst surfaces in catalytic reactions under high-temperature and high-pressure conditions, particularly mimicking actual processes, using infrared spectroscopy. A catalyst is a substance that promotes a chemical reaction without changing itself before and after the reaction. To improve the performance of a catalyst, it is crucial to investigate how substances adsorb and react on the catalyst's surface. TRC has made it possible to analyze catalytic reactions under controlled conditions of high temperature and high pressure (up to 700°C and 10 MPa) by using a special diffusion reflection infrared spectroscopy cell that can withstand high pressure, along with circulating reaction gases such as hydrogen and carbon monoxide. This enables the investigation of synthesis reactions of liquid hydrocarbons, which are alternative fuels to petroleum, under high-temperature and high-pressure conditions that mimic actual processes. In addition to optimizing the reaction conditions of catalysts, insights into the reaction mechanisms can also be obtained, which is expected to contribute to the design, development, and improvement of catalysts that are important for achieving carbon neutrality. For more details, please check the related links.
Added to bookmarks
Bookmarks listBookmark has been removed
Bookmarks listYou can't add any more bookmarks
By registering as a member, you can increase the number of bookmarks you can save and organize them with labels.
Free membership registration
HALT (Highly Accelerated Limit Test) is a testing method that exposes products to very high levels of temperature and vibration stress in a short period of time to reveal potential weaknesses. It has a proven track record with various devices such as smartphones and communication equipment, allowing for the early identification of structural defects and substrate issues before mass production, significantly reducing troubles in the market. We verify how much the product can withstand under harsh conditions and provide comprehensive support from investigating the causes of failures to developing countermeasures. For more details, please visit this page: https://www.toray-research.co.jp/analysis-evaluation/ana_071.html
Added to bookmarks
Bookmarks listBookmark has been removed
Bookmarks listYou can't add any more bookmarks
By registering as a member, you can increase the number of bookmarks you can save and organize them with labels.
Free membership registration
We are pleased to announce that we will be hosting the third webinar regarding the DNA chip "3D-GeneⓇ," which our company sells as an agent, aimed at those researching or considering extracellular vesicles. This webinar is divided into three parts: basic, measurement, and application. In the first (basic) and second (measurement) sessions, we had the honor of having Dr. Yusuke Yoshioka, a director of the Japanese Society for Extracellular Vesicles and a lecturer at the Department of Molecular Cell Therapy at the Medical Research Institute of Tokyo Medical University, present on research methods and the latest information regarding extracellular vesicles. The third session will introduce the industrial applications and evaluation methods of extracellular vesicles utilizing that content, presented by the Toray Group. We sincerely look forward to your participation. ● Seminar Registration - Participation Fee: Free - Format: Online Seminar If you wish to participate, please register through the "Related Links" below. ● Schedule January 29 (Wednesday) 17:00-17:40 (Live Broadcast) February 6 (Thursday) 19:00-19:40 (Rebroadcast) February 14 (Friday) 12:00-12:40 (Rebroadcast)
Added to bookmarks
Bookmarks listBookmark has been removed
Bookmarks listYou can't add any more bookmarks
By registering as a member, you can increase the number of bookmarks you can save and organize them with labels.
Free membership registration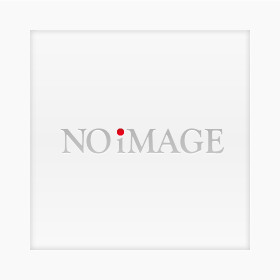
Analysis of the Characteristics of Antibody-Related Pharmaceuticals – Detailed Modification Analysis Including Charge Variants and Glycans Using LC-MS and icIEF-UV/MS – < Event Overview > Date and Time: January 16, 2025 (Thursday) 15:00 - 16:00 Format: Online (Zoom) 1. Analysis of Charge Heterogeneity of Antibody-Related Pharmaceuticals Using the Intabio ZT System (Ryo Yokoyama, AB Sciex Co., Ltd.) 2. Case Studies of Characteristic Analysis of Biopharmaceuticals Using Mass Spectrometry (Satoko Ota, Toray Research Center, Inc.) 3. Improving Work Efficiency in Protein Pharmaceutical Analysis Using MS Data Analysis Software Byos (Ayako Kurimoto, Protein Metrics) ◆ Detailed Page for This Webinar https://proteinmetrics.com/%e6%8a%97%e4%bd%93%e9%96%a2%e9%80%a3%e5%8c%bb%e8%96%ac%e5%93%81%e3%81%ae%e7%89%b9%e6%80%a7%e8%a7%a3%e6%9e%90/
Added to bookmarks
Bookmarks listBookmark has been removed
Bookmarks listYou can't add any more bookmarks
By registering as a member, you can increase the number of bookmarks you can save and organize them with labels.
Free membership registration
Toray Research Center, Inc. will hold an online seminar introducing the latest analytical technologies that contribute to achieving carbon neutrality. This seminar will be conducted in a web video streaming format. We will present cutting-edge technologies that support carbon neutrality research, such as catalytic reaction analysis of synthetic fuels and structural evaluation of Ni catalysts for CO2 reduction. Through this seminar, we aim to assist in solving research and development challenges and discovering new possibilities. Those who register during the seminar period will receive a URL to view the seminar video sequentially. We sincerely look forward to your participation. ◆ Latest Analytical Technology Seminar for Achieving Carbon Neutrality (Web Video Streaming) ◆ Dates: December 10 (Tuesday) to December 20 (Friday), 2024 | Online (Free) ◆ Program - Catalytic reaction and chemical composition analysis of synthetic fuels - Evaluation of the state and structure of Ni catalysts for CO2 reduction - Performance evaluation of CO2 absorbents using in situ IR measurements - Nanostructure evaluation of PEI films using positron annihilation lifetime method - Clarification of odor and discoloration causes in recycled polymers
Added to bookmarks
Bookmarks listBookmark has been removed
Bookmarks listYou can't add any more bookmarks
By registering as a member, you can increase the number of bookmarks you can save and organize them with labels.
Free membership registration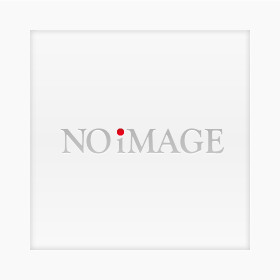
We will introduce the key factors for the introduction of Byos at the Toray Research Center and examples of its utilization. Date and Time: November 29 (Friday) starting at 1:00 PM (Doors open at 12:30 PM) Location: Breeze Plaza Address: 2-4-9 Umeda, Kita-ku, Osaka 530-0001, Breeze Tower
Added to bookmarks
Bookmarks listBookmark has been removed
Bookmarks listYou can't add any more bookmarks
By registering as a member, you can increase the number of bookmarks you can save and organize them with labels.
Free membership registration
We are pleased to announce that we will be hosting the second webinar regarding the DNA chip "3D-GeneⓇ," which our company sells as an agent, aimed at those who are researching or considering extracellular vesicles. This webinar will consist of three sessions covering the basics, measurement, and applications of extracellular vesicles. In the second session, we will once again have Dr. Yusuke Yoshioka, a director of the Japanese Society for Extracellular Vesicles and a lecturer at the Department of Molecular Cell Therapy at Tokyo Medical University, as our speaker. He will present on research methods and the latest information regarding extracellular vesicles. We sincerely look forward to your participation. ● Seminar Registration - Participation Fee: Free - Format: Online Seminar If you wish to participate, please register through the "Related Links" below. ● Schedule November 28 (Thursday) 17:00-17:45 (Live Broadcast) December 4 (Wednesday) 19:00-19:45 (Rebroadcast) December 13 (Friday) 12:00-12:45 (Rebroadcast)
Added to bookmarks
Bookmarks listBookmark has been removed
Bookmarks listYou can't add any more bookmarks
By registering as a member, you can increase the number of bookmarks you can save and organize them with labels.
Free membership registration
Our company (hereinafter referred to as "TRC") has utilized our know-how regarding the separation of various components in polymers and the two-dimensional liquid chromatography high-resolution mass spectrometer (hereinafter referred to as "2D-LC/HRMS") to become the first domestic contract analysis company to offer high-precision compositional analysis services for trace impurities contained in recycled polymers and the like. Trace impurities and degradation products in recycled polymers can potentially lead to performance degradation and discoloration of the polymers. However, conventional analytical methods have made it difficult to separate trace components and conduct structural analysis. Therefore, we have developed technology to enhance the separation capability of trace components, enabling their identification. This is expected to improve recycling processes and prevent discoloration. TRC aims to contribute to the realization of a sustainable society by providing information related to such material analysis and supporting material development.
Added to bookmarks
Bookmarks listBookmark has been removed
Bookmarks listYou can't add any more bookmarks
By registering as a member, you can increase the number of bookmarks you can save and organize them with labels.
Free membership registration
Our company (hereinafter referred to as "TRC") will start a contract analysis service to measure mechanical properties in micro-regions on the nanometer scale (one billionth of a meter) using high-performance nanoindenters, without exposure to the atmosphere. This will enable high-precision measurement of the properties of materials that deteriorate when exposed to oxygen or moisture in the air, such as lithium-ion batteries, organic EL, and catalyst-related materials. All-solid-state lithium-ion batteries are attracting attention as next-generation batteries, and the mechanical properties of the materials that make up the batteries are crucial for the performance of output and cycle life. We have successfully applied this method to all-solid-state lithium-ion batteries, which require handling without atmospheric exposure, and for the first time in the world, we have obtained the elastic modulus and hardness of active materials and solid electrolytes at any location within the electrode, as well as three-dimensional shape images. By providing accurate information on the mechanical properties of active materials and solid electrolytes, which are essential for the development of stable, safe, and high-performance all-solid-state lithium-ion batteries, we will support the development of new products.
Added to bookmarks
Bookmarks listBookmark has been removed
Bookmarks listYou can't add any more bookmarks
By registering as a member, you can increase the number of bookmarks you can save and organize them with labels.
Free membership registration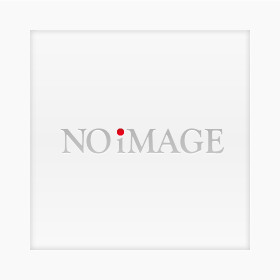
We will be hosting a webinar for those who are researching or considering extracellular vesicles regarding our DNA chip "3D-GeneⓇ," which we distribute as an agent. The first session will feature Dr. Yusuke Yoshioka, a director of the Japanese Society for Extracellular Vesicles and a lecturer at the Department of Molecular Cell Therapy, Medical Research Institute, Tokyo Medical University. We sincerely look forward to your participation. ● Seminar Registration - Participation Fee: Free - Format: Online Seminar If you wish to participate, please register via the URL below or through the "Related Links." https://trdna-webinar.v2.nex-pro.com/campaign/71725/apply?np_source=TR ● Schedule October 22 (Tuesday) 17:00-17:45 (Live Broadcast) October 31 (Thursday) 17:00-17:45 (Rebroadcast) November 8 (Friday) 12:00-12:45 (Rebroadcast)
Added to bookmarks
Bookmarks listBookmark has been removed
Bookmarks listYou can't add any more bookmarks
By registering as a member, you can increase the number of bookmarks you can save and organize them with labels.
Free membership registration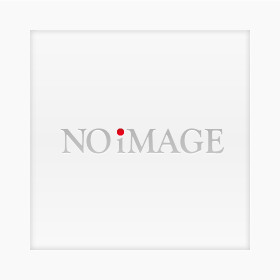
Toray Research Center, Inc. will be exhibiting at IMPACT2024. We will showcase structural analysis of adhesive interfaces, examples of plasma FIB processing of semiconductor devices, and analysis of Cu-Cu direct bonding, as well as our high-frequency characteristic evaluation service for materials (NXTEC). Please be sure to visit our booth. We look forward to seeing you. Date: October 22-25, 2024 Location: Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 1
Added to bookmarks
Bookmarks listBookmark has been removed
Bookmarks listYou can't add any more bookmarks
By registering as a member, you can increase the number of bookmarks you can save and organize them with labels.
Free membership registration
Our company (hereinafter referred to as "TRC") has launched a service that integrates a pyrolysis and catalytic reaction furnace, a pressure controller, and a unique gas introduction mechanism into a gas chromatography-mass spectrometry (GC/MS) system, enabling high-precision online qualitative and quantitative analysis of products in catalytic reactions. Catalysts are substances that can facilitate chemical reactions at low energy and are one of the key materials for achieving carbon neutrality (hereinafter referred to as "CN"). In recent years, there has been a demand for better catalysts and reaction processes to conduct desired reactions with high selectivity, high efficiency, and low cost. TRC has made it possible to use GC/MS for detecting catalytic reaction products and to perform online analysis that simulates various catalytic reaction conditions, allowing for more precise qualitative and quantitative analysis compared to conventional catalytic reaction evaluation devices. This is expected to lead to more effective catalyst screening and optimization of reaction processes. By providing detailed information related to the reaction products of catalysts, we aim to contribute to the realization of a sustainable society through support in material development.
Added to bookmarks
Bookmarks listBookmark has been removed
Bookmarks listYou can't add any more bookmarks
By registering as a member, you can increase the number of bookmarks you can save and organize them with labels.
Free membership registration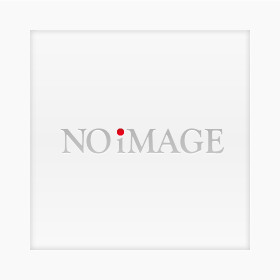
Our company (hereinafter referred to as "TRC") has launched a messenger RNA (hereinafter referred to as "mRNA") nucleotide sequence analysis service using mass spectrometry under original conditions that we have established. mRNA is being applied to various pharmaceuticals, including the novel coronavirus vaccine. To ensure the quality of mRNA-based pharmaceuticals, it is necessary to confirm that the mRNA has the nucleotide sequence as designed. However, current common analytical methods result in the loss of information about chemically modified bases during the preprocessing stage. In response, TRC has established a technique to analyze the nucleotide sequence of mRNA, including chemically modified bases, by fragmenting mRNA with a molecular weight of over one million using enzymes and measuring it with mass spectrometry. The service utilizing this technology will contribute to the quality assurance of mRNA-based pharmaceuticals.
Added to bookmarks
Bookmarks listBookmark has been removed
Bookmarks listYou can't add any more bookmarks
By registering as a member, you can increase the number of bookmarks you can save and organize them with labels.
Free membership registration
The technical information magazine The TRC News provides the latest information on analytical techniques that are useful for research and development, resolving production troubles, and quality control. **Abstract** Nucleic acid drugs generate impurities such as nucleotide deletions, adducts, and desulfurated forms during their synthesis process. Additionally, thiophosphate modifications aimed at improving the safety and efficacy of nucleic acid drugs can lead to the formation of stereoisomers due to the chiral nature of phosphorus atoms. Separating and purifying these impurities and isomers can pose challenges in the quality control of nucleic acid drugs. Ion mobility is a new technology that separates ionized compounds based on differences in collision cross-section area and charge, and it is gaining attention as an effective means for separating these impurities. In this study, we investigated the separation conditions for these impurities using ion mobility and confirmed the separation of nucleic acid impurities such as deletions and desulfurated forms. **Table of Contents** 1. Introduction 2. Ion Mobility Separation 3. Analytical Examples 4. Conclusion 5. Final Remarks
Added to bookmarks
Bookmarks listBookmark has been removed
Bookmarks listYou can't add any more bookmarks
By registering as a member, you can increase the number of bookmarks you can save and organize them with labels.
Free membership registration
The technical information magazine The TRC News provides the latest information on analytical techniques that are useful for research and development, solving production troubles, and quality control. **Abstract** The surface plasmon resonance (SPR) method is gaining attention for the analysis and evaluation of intermolecular interactions and quantification. The Sierra SPR-24Pro (Bruker) features 24 sensor spots, enabling high-throughput and rapid measurements from optimal condition exploration to evaluation of multiple samples. This article introduces Sierra SPR's unique kinetics analysis technology that does not use regeneration solutions, and presents kinetics analysis results of antibodies that exhibit very strong affinity, which have traditionally been difficult or time-consuming to analyze. Additionally, we report the development of a highly sensitive quantification method for Host Cell Proteins (HCP) using SPR. **Table of Contents** 1. Introduction 2. Kinetics Analysis 3. Quantification of HCP 4. Conclusion
Added to bookmarks
Bookmarks listBookmark has been removed
Bookmarks listYou can't add any more bookmarks
By registering as a member, you can increase the number of bookmarks you can save and organize them with labels.
Free membership registration
The technical information magazine The TRC News provides the latest information on analytical techniques that are useful for research and development, solving production troubles, and quality control. **Abstract** Single Particle ICP-MS (hereafter spICP-MS) is a method that utilizes the high sensitivity and elemental selectivity of ICP-MS to detect tiny and trace particles containing specific metals, allowing for the acquisition of their concentration and particle size distribution. This article introduces the principles of spICP-MS and presents a case study measuring metal particles in photoresist. **Table of Contents** 1. Introduction 2. Principles and Features of spICP-MS 3. Direct Introduction Method for Organic Solvents 4. Analysis of Al, Fe, and Cu Particles in Photoresist 5. Conclusion
Added to bookmarks
Bookmarks listBookmark has been removed
Bookmarks listYou can't add any more bookmarks
By registering as a member, you can increase the number of bookmarks you can save and organize them with labels.
Free membership registration
The technical information magazine The TRC News provides the latest information on analytical techniques that are useful for research and development, resolving production troubles, and quality control. [Abstract] The accuracy of analytical values when quantifying inorganic elements in various materials using ICP emission spectrometry depends on the validity of the dissolution method and its effectiveness. This paper introduces specific points to be particularly mindful of when quantifying boron (B). [Table of Contents] 1. Introduction 2. Chemical pretreatment for boron analysis 3. Conclusion
Added to bookmarks
Bookmarks listBookmark has been removed
Bookmarks listYou can't add any more bookmarks
By registering as a member, you can increase the number of bookmarks you can save and organize them with labels.
Free membership registration
The technical information magazine The TRC News provides the latest information on analytical techniques that are useful for research and development, solving production troubles, and quality control. **Abstract** In the development and manufacturing of semiconductor devices, understanding the structural changes of materials during thermal processing is extremely important. By using heating in-situ TEM, it is possible to visualize the thermal behavior of materials during heat treatment at the nanometer level, gaining new insights into structural changes that can aid in process development such as film quality control. This paper introduces case studies using heating in-situ TEM to analyze (1) the crystallization growth mechanism of amorphous silicon films in conjunction with crystal structure analysis, (2) the thermal behavior of metal stacked films in conjunction with elemental analysis, and (3) the observation of the crystallization growth process of thin film ruthenium films in a planar configuration. **Table of Contents** 1. Introduction 2. Overview and Features of Heating In-Situ TEM 3. Case Studies of Heating In-Situ TEM Analysis 4. Conclusion
Added to bookmarks
Bookmarks listBookmark has been removed
Bookmarks listYou can't add any more bookmarks
By registering as a member, you can increase the number of bookmarks you can save and organize them with labels.
Free membership registration
The technical information magazine The TRC News provides the latest information on analytical techniques that are useful for research and development, solving production troubles, and quality control. **Abstract** In measuring contact angles, the use of X-ray CT (computed tomography) methods, which can non-destructively capture the internal structure of samples in three dimensions, is effective for micro-regions, uneven shapes, and within materials. The contact angle measured in micro-regions using X-ray CT is significantly influenced by droplet size, the heterogeneity of the sample surface condition, and the shape of the contact surface. Therefore, it is important to evaluate these factors rather than simply comparing the magnitude of the contact angle. Here, we present results that verify these influences using three-dimensional observation data from polyethylene films and nylon threads. **Table of Contents** 1. Introduction 2. Influence of Droplet Size on Contact Angle 3. Contact Angle Measurement Using X-ray CT in Fibers 4. Conclusion
Added to bookmarks
Bookmarks listBookmark has been removed
Bookmarks listYou can't add any more bookmarks
By registering as a member, you can increase the number of bookmarks you can save and organize them with labels.
Free membership registration
The technical information magazine The TRC News provides the latest information on analytical techniques useful for research and development, solving production troubles, and quality control. **Abstract** Using mercury probes (Hg-Probe) and various physical analysis methods, we investigated in detail the relationship between the electrical properties and film quality of SiO2 films deposited on Si substrates using different methods. Compared to thermally oxidized SiO2 films, SiO2 films deposited by chemical vapor deposition (CVD) were found to have higher moisture and hydroxyl group content, and lower order in the SiO2 network structure, as revealed by RBS, XPS, FT-IR, and SIMS. C-V measurement results using Hg-Probe showed that SiO2 films deposited by plasma CVD have a high positive charge density, while those deposited by ozone CVD exhibit a high density of mobile charges, and it was confirmed that there is a correlation between moisture content and relative permittivity. I-V measurements also indicated that the leakage current of SiO2 films deposited by ozone CVD, which have high moisture content, is significant. Additionally, C-V measurements combined with wet etching confirmed that SiO2 films deposited by plasma CVD have a spread in charge distribution near the interface. **Table of Contents** 1. Introduction 2. Experiment 3. Results and Discussion 4. Conclusion
Added to bookmarks
Bookmarks listBookmark has been removed
Bookmarks listYou can't add any more bookmarks
By registering as a member, you can increase the number of bookmarks you can save and organize them with labels.
Free membership registration
The technical information magazine The TRC News provides the latest information on analytical techniques that are useful for research and development, solving production troubles, and quality control. **Abstract** In achieving a sustainable society, the development of energy-efficient and low-cost separation and purification technologies using membranes with excellent permeability is expected in various fields such as energy, semiconductors, and healthcare. Since the permeability of membranes is governed by their pore structure, techniques for evaluating advanced pore structures become crucial. Here, we introduce an overview of the mercury permeation method developed independently by the Toray Research Center, along with comparative examples with existing methods, demonstrating that the mercury permeation method is capable of selectively evaluating the nano pore diameter of functional layers. **Table of Contents** 1. Introduction 2. Overview of the Mercury Permeation Method 3. Case Studies Applying the Mercury Permeation Method 4. Conclusion
Added to bookmarks
Bookmarks listBookmark has been removed
Bookmarks listYou can't add any more bookmarks
By registering as a member, you can increase the number of bookmarks you can save and organize them with labels.
Free membership registration
The technical information magazine The TRC News provides the latest information on analytical techniques that are useful for research and development, solving production troubles, and quality control. **Abstract** Infrared spectroscopy is a method for obtaining information about molecular structure by measuring infrared absorption due to molecular vibrations. Utilizing photothermal conversion, O-PTIR (Optical Photothermal IR Spectroscopy) enables infrared analysis with sub-micron spatial resolution and non-contact measurement. This paper presents a case study of measuring non-fixed cells under physiological conditions to visualize the distribution and localization of cellular components (such as proteins and nucleic acids). **Table of Contents** 1. Introduction 2. Overview and Features of O-PTIR 3. Analysis of Suspended Living Cells (Budding Yeast) in Water - Comparison of Intracellular Spectra - 4. Analysis of Suspended Living Cells (Budding Yeast) in Water - Distribution of Cellular Components - 5. Conclusion
Added to bookmarks
Bookmarks listBookmark has been removed
Bookmarks listYou can't add any more bookmarks
By registering as a member, you can increase the number of bookmarks you can save and organize them with labels.
Free membership registration
The technical information magazine The TRC News provides the latest information on analytical techniques that are useful for research and development, solving production troubles, and quality control. **Abstract** Spectroscopic ellipsometry is known as a method for measuring changes in the polarization state of light to evaluate optical constants (refractive index and extinction coefficient) and film thickness. This article presents analysis examples using the high-speed spectroscopic ellipsometer M-2000UI, which was introduced in 2021, focusing on the temporal changes immediately after spin-coating PVA films and the evaluation of inclined etching of silicon insulating films. **Table of Contents** 1. Introduction 2. About Ellipsometry 3. Temporal Changes Immediately After Spin-Coating PVA Films 4. Evaluation of Inclined Etching of Silicon Insulating Films 5. Conclusion
Added to bookmarks
Bookmarks listBookmark has been removed
Bookmarks listYou can't add any more bookmarks
By registering as a member, you can increase the number of bookmarks you can save and organize them with labels.
Free membership registration
The technical information magazine The TRC News provides the latest information on analytical techniques that are useful for research and development, solving production troubles, and quality control. [Abstract] Molecular interaction analysis is an indispensable method in the study of life phenomena and the development of therapeutic drugs. The information on interactions obtained by different methods varies; for instance, surface plasmon resonance provides kinetic parameters of interactions, while isothermal titration calorimetry can acquire thermodynamic parameters of interactions. This paper introduces comprehensive analysis cases of interactions using multiple methods through multifaceted analysis. [Table of Contents] 1. Introduction 2. Surface Plasmon Resonance / Isothermal Titration Calorimetry 3. Analysis of the Interaction between STING and cGAMP 4. Conclusion
Added to bookmarks
Bookmarks listBookmark has been removed
Bookmarks listYou can't add any more bookmarks
By registering as a member, you can increase the number of bookmarks you can save and organize them with labels.
Free membership registration
The technical information magazine The TRC News provides the latest information on analytical techniques that are useful for research and development, resolving production troubles, and quality control. **Abstract** In recent years, as the demand for data integrity (DI) in the pharmaceutical industry has increased, pharmaceutical companies and contract testing organizations are required to respond accordingly. The Toray Research Center's CMC Analytical Research Department (hereinafter referred to as CMC) conducts pharmaceutical analysis under a GMP framework as a contract testing organization. In response to the growing inquiries and requests regarding DI from various customers, we have launched a DI project to address these needs. This article introduces CMC's initiatives for DI compliance. **Table of Contents** 1. Recent developments regarding DI 2. Launch of the DI project 3. Initiatives related to equipment 4. Initiatives related to documentation 5. Conclusion
Added to bookmarks
Bookmarks listBookmark has been removed
Bookmarks listYou can't add any more bookmarks
By registering as a member, you can increase the number of bookmarks you can save and organize them with labels.
Free membership registration
The technical information magazine The TRC News provides the latest information on analytical techniques that are useful for research and development, solving production troubles, and quality control. [Abstract] Ion mobility mass spectrometry can separate structural isomers with the same mass that traditional mass spectrometers cannot, making it promising for various applications such as characterization of antibody drugs and ADCs, glycan structure analysis, binding site analysis, peptide mapping, impurity analysis of nucleic acid drugs, bioanalysis of oligonucleotides, and comprehensive analysis of biomarkers. This article introduces the features of the ion mobility mass spectrometer introduced at the Toray Research Center and presents examples of disulfide bond position analysis and glycan structure analysis. [Table of Contents] 1. Introduction 2. Overview of the Analytical Method 3. Analytical Examples 4. Conclusion
Added to bookmarks
Bookmarks listBookmark has been removed
Bookmarks listYou can't add any more bookmarks
By registering as a member, you can increase the number of bookmarks you can save and organize them with labels.
Free membership registration
**Abstract** Gallium oxide (Ga2O3), which has a larger bandgap than SiC and GaN, is gaining attention as a new power device material. With the development of thin film growth technologies for device applications, the importance of analysis and evaluation techniques for Ga2O3 thin films is expected to increase. This paper introduces cases of crystal structure analysis of Ga2O3 films fabricated on sapphire substrates, as well as the evaluation of impurities and defects. **Table of Contents** 1. Introduction 2. Samples 3. Analysis Results 4. Conclusion
Added to bookmarks
Bookmarks listBookmark has been removed
Bookmarks listYou can't add any more bookmarks
By registering as a member, you can increase the number of bookmarks you can save and organize them with labels.
Free membership registration
**Abstract** Spectroscopic analysis techniques utilizing near-field light localized at the tips of metal chips are highly anticipated methods for analyzing chemical structures in the nanometer range. Techniques such as tip-enhanced Raman spectroscopy and near-field Raman spectroscopy are representative methods, and various studies have been conducted on their principles and applications. This paper presents examples of their application in material analysis and discusses their practicality for material characterization. **Table of Contents** 1. Introduction 2. Crystal structure analysis of CNTs using TERS 3. Stress analysis at the SiO2/SiC interface using SNOM-Raman 4. Conclusion
Added to bookmarks
Bookmarks listBookmark has been removed
Bookmarks listYou can't add any more bookmarks
By registering as a member, you can increase the number of bookmarks you can save and organize them with labels.
Free membership registration
**Abstract** Differential Phase Contrast (DPC) - Scanning Transmission Electron Microscopy (STEM), one of the measurement techniques of STEM, enables the measurement of electric fields at microscopic regions. By applying this method to polymer alloys, we discovered that contrast of phase separation structures, which are difficult to observe with conventional electron microscopy, emerges. **Table of Contents** 1. Introduction 2. Visualization of Soft Materials through Elemental Analysis 3. Application of DPC-STEM Method 4. Conclusion
Added to bookmarks
Bookmarks listBookmark has been removed
Bookmarks listYou can't add any more bookmarks
By registering as a member, you can increase the number of bookmarks you can save and organize them with labels.
Free membership registration
**Abstract** In many cases, the analysis targets in surface analysis are limited to those that can be maintained in a vacuum. On the other hand, by applying the potential of high-speed ions, it is possible to bring the analysis probe out to atmospheric pressure. At TRC, we examined Rutherford backscattering spectroscopy (RBS) at atmospheric pressure and succeeded in its realization. This paper reports on depth analysis of solid/liquid interfaces using atmospheric pressure RBS, evaluation of depth distribution of quantum dots in HeLa cells, and depth analysis of hydrogen in wet samples using atmospheric pressure RBS/HFS (hydrogen forward scattering analysis). **Table of Contents** 1. Introduction 2. Solid/Liquid Interface Analysis 3. Application to Biological Samples 4. Development of Measurement System at TRC: Atmospheric Pressure RBS/HFS Analysis 5. Conclusion
Added to bookmarks
Bookmarks listBookmark has been removed
Bookmarks listYou can't add any more bookmarks
By registering as a member, you can increase the number of bookmarks you can save and organize them with labels.
Free membership registration
**Abstract** The state-of-the-art secondary ion mass spectrometry (SIMS) device, NanoSIMS 50L, enables imaging measurements with spatial resolution approximately two orders of magnitude higher than conventional SIMS, thanks to its ion beam with a probe diameter of about 50 nm and a highly efficient mass analysis system. This paper introduces the features of the NanoSIMS 50L device and analysis examples. **Table of Contents** 1. Introduction 2. Overview of the Analytical Device 3. Analysis Example of Hair Cross-Section 4. Analysis Example of SiC Semiconductor Devices 5. Conclusion
Added to bookmarks
Bookmarks listBookmark has been removed
Bookmarks listYou can't add any more bookmarks
By registering as a member, you can increase the number of bookmarks you can save and organize them with labels.
Free membership registration
**Abstract** In the development using new materials, it is expected that the functions of the materials will be fully utilized and applied in various applications. In this context, by understanding the basic functions of new materials and simultaneously conducting multifaceted examinations such as information gathering on application prospects and identifying challenges, we can connect the practical application of new materials to their extensive deployment. Here, taking CNF as an example, we will introduce the information obtained through technological development research regarding the situation surrounding CNF and the effective utilization of its functions. **Table of Contents** 1. Introduction 2. Results of the literature survey on CNF research 3. Conclusion
Added to bookmarks
Bookmarks listBookmark has been removed
Bookmarks listYou can't add any more bookmarks
By registering as a member, you can increase the number of bookmarks you can save and organize them with labels.
Free membership registration
**Abstract** In the research and development of CNF, the use of electron microscopy for observation has become a necessary evaluation across almost all material fields and research phases. Particularly for observing CNF dispersed in polymers using TEM, it is essential to employ the technique of "electron staining," which has been crucial for preparing TEM samples of polymer materials. In this presentation, we will introduce examples of morphological observations of composite materials using CNF, as well as observation cases of the CNF itself, structural analysis examples such as crystallinity measured by 13C solid-state NMR, and examples of compositional sugar analysis using acid hydrolysis HPLC-fluorescence detection. **Table of Contents** 1. Introduction 2. Overview of Morphological Observation 3. Observation Cases of CNF and CNF/Polymer 4. Evaluation of CNF Crystallinity 5. Compositional Sugar Analysis of CNF (HPLC-Fluorescence Detection) 6. Conclusion
Added to bookmarks
Bookmarks listBookmark has been removed
Bookmarks listYou can't add any more bookmarks
By registering as a member, you can increase the number of bookmarks you can save and organize them with labels.
Free membership registration
**Abstract** With the improvement of simulation technology, techniques for estimating physical properties have developed. On the other hand, there are often discrepancies between the estimated physical properties and the actual behavior of materials. One possible cause of this is that the parameters used in the simulation differ from those of the materials being used. This paper examines composite materials using cellulose nanofibers (CNF), a new material that has garnered attention in recent years, by comparing the orientation of CNF and the linear thermal expansion coefficient of the composite material between measured values and estimated values from simulations. Furthermore, the results of the evaluation of the impact of the parameters used in the simulation are presented. **Table of Contents** 1. Introduction 2. Samples 3. Measurement and Simulation Analysis Methods 4. Comparison of CNF Orientation 5. Comparison of Linear Thermal Expansion Coefficient (CTE) 6. Conclusion
Added to bookmarks
Bookmarks listBookmark has been removed
Bookmarks listYou can't add any more bookmarks
By registering as a member, you can increase the number of bookmarks you can save and organize them with labels.
Free membership registration
**Abstract** Using the TEM-based crystal orientation analysis system "ASTAR," it is possible to achieve higher spatial resolution than that of SEM-based EBSD (with spatial resolution of various EBSD methods being around tens of nanometers, while the ACOM-TEM method using ASTAR achieves 2 to 5 nm). Additionally, it is characterized by the ability to identify a greater variety of crystal structures. By obtaining crystal orientation maps, crystal phase maps, and grain size distributions that are difficult to acquire through conventional TEM analysis, quantitative interpretation becomes possible. Furthermore, since measurements can be taken in the same field of view as TEM observations, it allows for complex analyses combined with (S)TEM-EDX/EELS and the use of in-situ TEM. **Table of Contents** 1. Introduction 2. ACOM-TEM Method Using ASTAR 3. Examples of Analysis Using ASTAR 4. Conclusion
Added to bookmarks
Bookmarks listBookmark has been removed
Bookmarks listYou can't add any more bookmarks
By registering as a member, you can increase the number of bookmarks you can save and organize them with labels.
Free membership registration
**Abstract** Pulse NMR (TD-NMR, Time Domain NMR) is a technique specialized for obtaining relaxation times, unlike high-resolution NMR aimed at structural analysis. One characteristic of the relaxation times obtained from NMR is their high sensitivity to the state of the sample (such as the hardness of solid materials and the molecular motion of liquid samples). This paper presents examples of evaluating rubber materials and assessing the dispersibility of ink materials, utilizing this characteristic. **Table of Contents** 1. Introduction 2. Evaluation of Natural Rubber Degradation 3. Evaluation of the Dispersibility of Silver Nano Ink 4. Conclusion
Added to bookmarks
Bookmarks listBookmark has been removed
Bookmarks listYou can't add any more bookmarks
By registering as a member, you can increase the number of bookmarks you can save and organize them with labels.
Free membership registration
**Abstract** Compared to the most common ESR measurements using X-band (9.5 GHz) microwaves, ESR measurements using higher frequency microwaves are effective for improving the resolution of ESR spectra and spectral analysis. This paper presents analysis examples of fluorine-based resins, diamond powders, silica glass, and luminescent powders using newly introduced X-band and Q-band (34 GHz) ESR equipment. **Table of Contents** 1. Introduction 2. Features of the New ESR Equipment 3. High-Temperature ESR Measurement Examples of Fluorine-Based Resins 4. Q-Band ESR Measurement Examples 5. Conclusion
Added to bookmarks
Bookmarks listBookmark has been removed
Bookmarks listYou can't add any more bookmarks
By registering as a member, you can increase the number of bookmarks you can save and organize them with labels.
Free membership registration
**Abstract** In order to achieve the widespread adoption of solid-state batteries, it is necessary to solve various challenges such as improving characteristics, ensuring safety, and enhancing durability. Unlike liquid electrolyte lithium-ion batteries, the development of new evaluation techniques related to the material properties of solid electrolytes is expected to become increasingly important in the future. This paper introduces the latest analytical evaluation techniques that are useful for "material development" and "improving battery manufacturing processes" in the design and development of solid-state batteries, along with relevant case studies. **Table of Contents** 1. Introduction 2. Material Development 3. Improvement of Battery Manufacturing Processes 4. Conclusion
Added to bookmarks
Bookmarks listBookmark has been removed
Bookmarks listYou can't add any more bookmarks
By registering as a member, you can increase the number of bookmarks you can save and organize them with labels.
Free membership registration
**Abstract** Vulcanized rubber (natural rubber: NR, styrene-butadiene rubber: SBR, etc.) has been difficult to analyze chemically due to its insolubility in solvents. Therefore, by introducing a technique to cleave the sulfur cross-links that cause this insolubility and solubilize the rubber components, it has become possible to apply solution NMR and GPC, which are essential for structural analysis and physical property measurement of high molecular weight substances that were previously unattainable. This allows for more detailed analytical evaluations when combined with conventional methods. This paper presents examples of structural analysis and degradation analysis of vulcanized natural rubber. **Table of Contents** 1. Introduction 2. Cleavage of Sulfur Cross-links 3. Analysis of Vulcanized Natural Rubber 4. Application to Degradation Analysis 5. Conclusion
Added to bookmarks
Bookmarks listBookmark has been removed
Bookmarks listYou can't add any more bookmarks
By registering as a member, you can increase the number of bookmarks you can save and organize them with labels.
Free membership registration
**Abstract** On the surface of silica, there are hydroxyl groups known as silanol groups (Si-OH), which play a significant role in its physical properties such as hydrophobicity and hydrophilicity. Additionally, by bonding silane coupling agents, the chemical properties of the surface can be improved, making it widely used as a resin filler. Therefore, these silanol groups on the silica surface are important factors that influence not only the properties of silica itself but also the overall performance of the material. This paper introduces a method for accurately and sensitively quantifying silanol groups in a stable manner. **Table of Contents** 1. Introduction 2. Principle 3. Quantification of reactive silanol groups in silica particles 4. Quantification of surface silanol groups on silicon wafers 5. Changes in the amount of silanol groups due to heating 6. Conclusion
Added to bookmarks
Bookmarks listBookmark has been removed
Bookmarks listYou can't add any more bookmarks
By registering as a member, you can increase the number of bookmarks you can save and organize them with labels.
Free membership registration
**Abstract** With the diversification of drug discovery modalities and changes in healthcare, the required analytical techniques are becoming increasingly sophisticated. At the Toray Research Center, we are engaged in the development of new analytical methods and technologies to support the development of cutting-edge pharmaceuticals and biomarkers. Here, we will introduce analytical case studies related to nucleic acid medicines, antibody drugs/ADCs, and biomarkers/diagnostics. **Table of Contents** 1. Introduction 2. Analysis of Nucleic Acid Medicines 3. Analysis of Protein Medicines 4. Analysis of Biomarkers and Diagnostics 5. Conclusion
Added to bookmarks
Bookmarks listBookmark has been removed
Bookmarks listYou can't add any more bookmarks
By registering as a member, you can increase the number of bookmarks you can save and organize them with labels.
Free membership registration